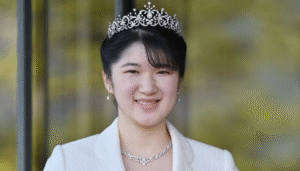高市早苗総裁の下で、自民党が日本維新の会との連立協議を進める動きが加速しています。
しかし、その背景には多くの国民が抱く「違和感」と「民意無視」への懸念が根強く存在しています。
7月の参院選で国民が示したのは、何よりもまず、止まらない物価高への早急な対策と、家計を支えるための減税でした。
国民の投票行動は「政治の信頼回復」よりも、「暮らしの再建」と「実感できる経済支援」を求める声として明確に表れました。
にもかかわらず、この3ヶ月間、既存の政党はいずれも具体的な物価対策や減税実施への工程を示さず、政局の駆け引きに終始しているように見えます。
街頭で耳にするのは

「これでは投票してもやっぱり何も変わらないじゃないか」
という失望の声。
SNS上でも



「結局、誰が政権を取っても暮らしは良くならない」
という諦めの投稿が目立ちます。
せっかく前回の参院選でわずかに上向いた投票率も、こうした空気の中では次の国政選挙で再び下がるおそれがあります。
特に、生活への切実な危機感から投票所へ足を運んだ若年層や無党派層ほど、「政治に託す意味」を見失い、離反するリスクが高まります。
その結果、政策の正当性が薄れ、物価高や税負担といった国民生活に直結する課題への対応がさらに遅れる可能性もあります。
今必要なのは、数合わせの政治ではなく、民意に正面から向き合い、期限と成果を明確にした実効性ある経済政策を打ち出すことです。
連立協議の背景と政治的思惑


2025年10月16日、自民党と日本維新の会は正式に連立政権樹立に向けた政策協議を開始しました。
公明党の離脱によって過半数を失った自民党は、高市早苗総裁の首相指名を確実にするため、急ピッチで維新との連携を進めています。
維新側は12項目に及ぶ政策要求を提示し、その中で「副首都構想」や「社会保障改革」を最優先課題として掲げました。
特に、副首都構想は大阪の経済再生と地方分権を象徴する政策として維新が長年掲げてきた看板政策であり、国政の場で再浮上させる狙いがあります。
一方、自民党にとっては、参院での安定多数を確保し、政権運営に支障をきたさないための現実的な選択といえます。
しかし、その協議の内実を冷静に見つめると、国民が今求めている「物価高対策」や「減税」といった生活直結型の政策議論がほとんど進んでいないことに気づきます。
さらに、維新が提示する政策の中でも、企業・団体献金禁止や政治資金の透明化といった政治倫理改革は優先順位が低く扱われており、国民が求める実質的な改革とは大きくかけ離れています。
吉村洋文代表自身も、企業・団体献金禁止を12番目に置き、「自民党がイエスと言うことはない」と発言しており、その姿勢からは政策実現への強い執念よりも、連立協議を政治的カードとして扱う思惑が透けて見えます。
高市総裁もまた、裏金問題を「決着済み」とする発言を繰り返しており、国民が最も注目する政治倫理問題は置き去りにされたままです。
その結果、この連立協議は国民生活よりも政権維持を優先した「数合わせ」の印象を強めています。
さらに、両党が掲げる社会保障改革も、年金制度や医療費負担の見直しといった国民に直接関わる課題に対しては具体策を欠き、抽象的な理念にとどまっています。
経済と生活の不安が続く中で、政治が自己保身の方向に動く現状に、国民の失望と疑念は一層深まっています。
参院選の民意を無視した数合わせの危うさ


7月の参院選では、自民党と公明党の与党が過半数を大きく割り込み、国民から厳しい審判を受けました。
加えて、日本維新の会も議席を減らし、両党ともに伸び悩みが鮮明になりました。
本来であれば、こうした結果は、国民が最優先で求めた物価高対策と減税に直ちに取り組むという明確なメッセージとして受け止め、具体策の提示と実行へと踏み出すべき合図でした。
しかし、そのわずか3か月後に、いずれも得票と議席を落とした政党同士が、反省と再設計より先に連立の座組みづくりに走る姿は、なぜ今なのかという強い違和感を拭えません。
選挙で縮小した民意の後押しを、政局上の多数派工作で補うかのような動きは、「暮らしの再建」という切実な要求から目をそらし、結果として民意の薄められた政権運営を招きかねません。
JBpressや朝日新聞、毎日新聞など複数の報道機関も、この動きを「民意の軽視」と論評しています。
特に、維新の政策要求において「副首都構想」が最優先される一方、国民が最も求める物価対策や減税の工程が見えない点が、批判の的となっています。
大阪で2度否決された「大阪都構想」を連想させる副首都構想を、国政レベルで優先的に押し出すことについても、今このタイミングで本当に求められているのかという疑問が広がっています。
なぜ、支持を減らした当事者同士がまず向き合うべきは、家計を直接下支えする即効性のある政策ではなく、政権延命につながる座組みの再編なのか――その順番の逆転こそが、連立自体への大きな違和感の核心なのだと思います。
維新内部にも広がる戸惑いと反発


維新の支持層の中からも、自民党との連立に対して強い懸念が噴出しています。
特に大阪以外の地域では、「維新が自民党化してしまうのではないか」という不安が広がっており、後援会長の一部からも「これでは支持を失う」との声が上がっています。
維新ジャーナルの参院選総括でも、「厳しい結果」とし、比例得票率が前回の14.8%から7.39%へと半減したことを反省材料として挙げていました。
その直後に自民党との連立に走ることは、支持者への裏切りとの見方も出ています。
さらに、今回の連立交渉の中で維新が条件として強く押し出している「副首都構想」に対しても、全国的に違和感の声が広がっています。
この構想は大阪の都市機能を強化し、東京一極集中を緩和するという名目で語られていますが、実際には巨額の公共工事を伴う可能性が高く、経済効果よりも財政負担への懸念が先に立つとの指摘も少なくありません。
特に大阪万博の準備と開催に巨額の税金が投入された直後であることから、



「またも大阪か」



「維新は結局、自分たちの地盤を潤すことしか考えていないのではないか」
といった冷ややかな視線が多くの国民の間に広がっています。
関西圏に偏った利益誘導のように映るこの政策姿勢に対し、地方都市や首都圏では「国全体の成長を見据えた政策ではなく、地域政党的な自己中心性が透けて見える」との批判も噴出しています。
党内でも「副首都構想の実現のために連立はやむを得ない」という前向きな意見がある一方、「時期尚早」「自民と手を組むのは危険」とする慎重論が根強く存在します。
特に若手議員を中心に「閣外協力にとどめるべき」との声が強く、党内の温度差が際立っています。
維新が本当に目指すべきは大阪のための政治ではなく、全国規模での改革の実現であるはずだという指摘も増えており、今回の連立姿勢はその理念との乖離をさらに浮き彫りにしているのです。
民意軽視の政治がもたらす未来


参院選で示された民意は、「政治刷新」への強い期待でした。
にもかかわらず、自民・維新両党が数合わせの連立協議に走る姿は、民主主義の根幹を揺るがす行為といえます。
しかも、参院選からすでに3か月以上が経過しているにもかかわらず、国会は未だ開かれず、政府与党による本格的な政策審議の場が設けられていません。
高市総裁の就任をめぐる自民党総裁選や、その後に続く連立交渉の混乱に時間と労力が費やされる一方で、国民が最も求める早急な物価高対策や実効性のある経済政策は一向に進展していません。
生活必需品や公共料金の値上がりが止まらない中で、



「政治家たちは私たちの暮らしの苦しさを理解していない」
という不満と怒りが、街頭やSNS上で日々膨らんでいます。
地方の商店街や家庭の声を拾えば、



「もう限界」



「このままでは冬を越せない」
という悲鳴が聞こえますが、永田町からは現場の切実な声に寄り添う気配は薄く、国民との間に深い温度差が広がっています。
政治評論家の中には、「今の政権は、政局と党内勢力図の維持にしか関心がない」と指摘する声もあり、まさにその言葉を裏づけるように、国会審議が後回しにされている現実があります。
もしこのまま連立が成立すれば、政治不信はさらに深まり、次の衆院選では無党派層の離反が加速する可能性もあります。
国民の生活感覚と政治家の危機意識との乖離がこれほどまでに広がった状況は、戦後政治の中でも極めて異例です。
政治評論家の多くが指摘するように、



「民意を軽んじた政権維持は、いずれ国民の強い反発を招く」
という事実を、政権与党は真摯に受け止めるべきです。
まとめ
自民党と日本維新の会の連立協議は、国民にとって本当に望ましい政治の姿を描いているのでしょうか。
参院選で示された物価高対策と減税の強い要請を置き去りにし、政権延命のための数合わせに走る姿は、民意を踏みにじる行為だと受け止められても無理はありません。
高市早苗総裁と吉村洋文代表が今こそ問われているのは、党利党略ではなく、生活者の目線に立った即効性のある政策で国民の信頼をどう取り戻すかという一点です。
政治の本来の使命は、権力の維持ではなく、民意の反映にあります。
参院選から3か月以上も国会が開かれず、物価高に直結する家計支援や減税の具体策が示されない現状は、その原点からの逸脱にほかなりません。
このまま選挙の審判を軽んじた連立が進めば、いずれ自民・維新両党にとって深刻なブーメランとなって跳ね返り、投票率の低下と無党派層の離反というかたちで可視化されるはずです。
私個人の意見としては、参院選後のこの体たらくな動きを目の当たりにすると、「こんなことしかできないのなら、国会議員の数を思い切って半分にし、責任を持って仕事ができる方々だけに絞ってほしい」と強く思います。
定数の見直しは目的ではなく手段ですが、少数精鋭で迅速に議論と決定を行い、期限と成果を伴う政策を実行する体制に改めることが、今の政治に最も欠けている信頼とスピードを取り戻す近道だと考えます。