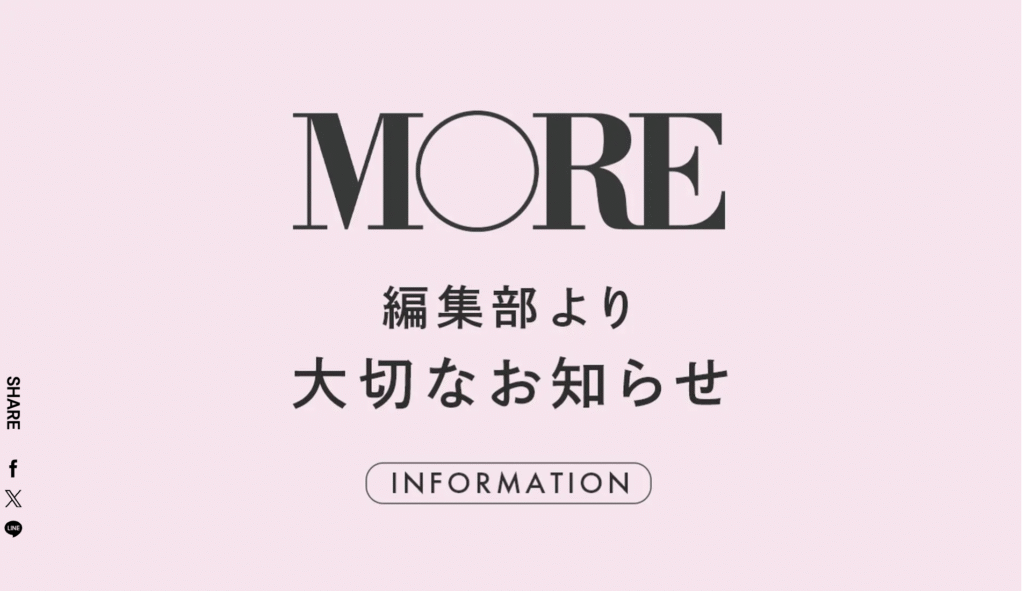
1977年に創刊した女性ファッション誌「MORE(モア)」が、2025年9月26日発売の「Autumn 2025」号をもって休刊を迎えました。
創刊から約48年もの歴史を持つこの雑誌は、働く20代女性のファッションやライフスタイルを提案する存在として長らく愛されてきました。
時代ごとに読者の心をつかみ、1980年代から1990年代にかけては若い女性たちのバイブル的存在として支持を集め、オフィスカジュアルや休日のリラックスコーデなど、その時代のトレンドを鮮やかに切り取ってきたのです。
誌面に登場するモデルや女優のファッションは瞬く間に街中に広がり、リアルクローズを中心とした提案が読者の生活に直接結びついていました。
しかし、発行部数の急激な減少や広告市場の変化、そしてスマートフォンやSNSの台頭による情報の流通経路の激変、デジタル化の波など、さまざまな要因が重なり、今回の決断に至ったのです。
ここでは、MOREの休刊理由、部数推移、歴史、そして出版業界全体の構造変化を踏まえた流れについて、従来の紙媒体が果たしてきた役割も含めて詳しく解説していきます。
MORE休刊の理由とは

集英社が公表した休刊理由は「社として総合的に判断した」とされています。
ですが、背景には出版業界全体を取り巻く深刻な構造変化があります。
まず、読者層の変化が大きな要因です。少子化やライフスタイルの多様化により、従来の20代女性を中心とした購買層が縮小しました。
さらに情報摂取の主戦場は紙からスマートフォンへと完全に移行し、20代女性の一日のメディア消費ではSNSが長時間を占め、雑誌(紙)はごく短時間にとどまるという構図が定着しました。
その結果、読者は「今月の特集」を待つより、InstagramやTikTok上の短尺動画で即時に着こなしやメイクを学び、ハッシュタグ経由で在庫確認から購入までを短時間で完了させる行動様式へと移っています。
紙面の編集サイクルでは、この“いま欲しい”スピード感に追随しにくかったのです。
次に、広告市場の構造転換です。
総広告費は拡大している一方で伸びの主役はインターネット広告であり、雑誌広告の市場シェアは極小化しています。
化粧品やファッションブランド各社は、インフルエンサーを活用した動画・ライブ配信・UGC連動の施策に予算を厚く配分し、指名検索よりもアルゴリズムによるレコメンド起点の導線を重視するようになりました。
紙面の純広やタイアップは効果測定が難しく、CPCやCPAで可視化できるデジタル施策に劣後しやすい状況が続いたことも、収益の目減りに拍車をかけました。
加えて、コストの硬直化が収支を圧迫しました。
撮影・スタイリスト・ヘアメイク・ロケバス・スタジオといった制作費に、用紙価格や物流費の上昇が重なり、発行部数の減少を原価で吸収できない状態が常態化しました。
従来の「広告+販売」で成り立つ二元モデルは、EC連動やライブコマース、サブスクリプション、データドリブンなレコメンドといった新しい収益回路を持つ競合(WebメディアやSNS発メディア)に対して相対的に不利になりました。
競合誌の中には、Web動画やライブコマースへの投資を強めて部数減のスピードを緩和した例もありますが、MOREは2023年の季刊化以降、SNS連動やインフルエンサー協業の厚みで後れを取り、デジタル投資を一段と加速させるには至らなかったという側面があります。
こうした、需要の縮小・広告のデジタル偏重・コスト上昇・モデル陳腐化という複合要因が同時に作用し、ビジネスモデルの持続が難しくなったのです。
発行部数の推移と衰退の過程

MOREは創刊から80年代後半にかけて絶頂期を迎えました。
1988年10月号では最高発行部数86万部を記録し、90年代も80万部前後を維持する人気雑誌でした。
誌面には旬のトップモデルや女優が登場し、当時のオフィススタイルやトレンドを象徴する着こなしが瞬時に全国に広がり、若い女性の憧れや実践的なおしゃれの手引きとして機能していました。
その一方で、2000年代に入ると右肩下がりが続き、2006年には約59.8万部、2010年には42.6万部、2013年には40.2万部まで減少しました。
リーマンショックなどの景気後退や広告主の雑誌離れが進んだことも打撃となり、誌面のボリュームや広告ページも徐々に縮小していきました。
その後も部数は減り続け、2023年にはついに月刊から季刊へ移行し、発行頻度の減少に伴って存在感が希薄化。
直近の平均発行部数は4万5千部程度にまで落ち込み、かつての勢いを取り戻すことはできませんでした。
全盛期との落差は実に約20分の1にあたり、この数値は単にMOREだけでなく、日本の雑誌市場全体の縮小とデジタルシフトの加速を象徴するものと言えるでしょう。
MOREの歴史とその役割

MOREは1977年に創刊され、働く20代女性をターゲットに「シンプルで可愛い」スタイルを提案し続けてきました。
当時の20代女性は「OL」と呼ばれ、社会に出て自分らしさを表現する時代を迎えていました。
高度経済成長の余韻が残る中で、都市部のオフィス街に通う若い女性たちが自立心を育み、仕事も恋愛もファッションも積極的に楽しむ姿を誌面に映し出していたのです。
MOREはそのライフスタイルを映し出す雑誌として、ファッションだけでなく恋愛、キャリア、ライフデザインに関する記事を幅広く取り上げてきました。
誌面には人気モデルや女優が登場し、明るく元気なイメージを体現しながら、読者が抱える「自分らしさと社会とのバランス」というテーマに寄り添いました。
さらに、時代の変化に合わせて誌面は柔軟に進化し、バブル期には華やかなブランドコーデや海外旅行特集を組み、2000年代にはプチプラやファストファッションを取り入れた等身大の提案を展開しました。
早くからファストファッションやプチプラコーデを取り入れ、多くの女性に「自分にもできるおしゃれ」を届けてきたのです。
加えて、読者参加型の企画やインタビュー記事も豊富で、誌面に登場する読者モデルや一般女性の声を反映することで共感を生み出しました。
ときには働く女性の悩みやキャリア設計を特集することで、単なるファッション誌を超えて「働く女性のパートナー」としての役割を果たし続けていたのです。
出版業界とファッション誌市場の変化

MOREの休刊は単に一誌の問題ではなく、日本の出版業界が直面している構造的な課題を示す象徴的な出来事です。
女性誌市場は1996年をピークに縮小を続け、2020年の発行部数はおよそ1億冊を割り込む水準となりました。
広告市場ではインターネット広告が急拡大し、2024年には総広告費7兆6730億円のうち半分以上を占めるまでに成長。
逆に雑誌広告のシェアはわずか2.3%にまで縮小しました。
ファッションブランドもSNSでのインフルエンサーマーケティングを中心に戦略を展開し、雑誌の存在感は急速に希薄化。
さらに、制作費の固定的な高さが出版社の収益を圧迫し続け、従来の「広告+販売」の二本柱モデルが機能不全に陥ったのです。
加えて、流通面の変化も痛打となりました。
書店数の減少やコンビニの雑誌棚縮小により、偶発的な出会い買いの機会が目に見えて減少し、定期購読離れと返品率の上昇が収益を圧迫しました。
用紙・インキ価格や製本・配送コストの上昇に加え、物流現場の人手不足や働き方改革の影響による配送効率の低下が、紙媒体の原価構造を一段と厳しくしています。
編集サイクルも月次から隔月・季刊へと延長される中、SNSでは「今日の新作」「今夜のライブ配信」といった即時性が評価され、情報鮮度での競争は不利になりました。
マーケティングの潮流も雑誌に逆風でした。
ブランド各社はパフォーマンス指標で効果を測定できるデジタル施策に投資をシフトし、ライブコマースやクリエイターコラボ、UGCを核にした販売導線を整備しています。
サードパーティクッキー規制の強化で、媒体横断のマス露出よりも、顧客データを保有するプラットフォームとの連携や、自社メディア・コミュニティ運営の価値が相対的に高まりました。
雑誌側も付録や別冊、ブランドムック、イベント収益など多角化を試みましたが、恒常的な収益エンジンに育てるには至らず、在庫リスクや制作負担の増大が足かせとなりました。
競合誌の「with」「CanCam」「JJ」も形態変更や不定期刊行を余儀なくされ、デジタル動画・EC連携・コミュニティ運営へと重心を移すことで、紙のマスモデルからの脱却を急いでいます。
MOREの休刊はその延長線上にあり、紙媒体の存在意義を「情報の器」から「体験と購買のハブ」へ再定義しない限り、持続可能性を確保しにくいという、業界共通の命題を浮き彫りにした出来事だと言えます。
まとめ
女性ファッション誌「MORE」の休刊は、紙媒体からデジタルへの大きな転換点を示す出来事です。
創刊以来、約48年にわたり多くの女性にファッションとライフスタイルの指針を届けてきたMOREは、全盛期には80万部を超える人気を誇りました。
しかし、読者層の変化や広告市場のシフト、デジタル化の波に対応しきれず、最終的には休刊に至りました。
とはいえ、集英社は「MORE JAPAN by SHUEISHA」として地方創生やデジタル発信の場でブランドを継承する方針を掲げています。
紙の時代を彩ったMOREは幕を閉じましたが、その名前は新たな形で未来へと受け継がれていくのです。
さらに、この休刊は単に一誌の終焉ではなく、女性誌市場全体が抱える課題を象徴しています。
紙からデジタルへの転換の中で、媒体の役割は「情報を伝える」だけでなく「体験をつなぐ」ことへと拡張されつつあり、MOREの歴史は今後のメディアの方向性を考える上で貴重な教訓を与えてくれます。
出版業界全体にとっても、この出来事は新しい時代の生存戦略を模索する大きなきっかけとなるでしょう。






